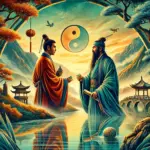烏合の衆(うごうのしゅう)
「烏合の衆」は、しばしば統制の取れない寄せ集めの集団として使われます。しかしながら、その背景にある歴史的逸話や教訓には、あまり注目されていないようですが、実は現代ビジネスやリーダーシップに役立つ重要なポイントが隠されています。
そこで、故事の出典や歴史的背景を掘り下げ、その教訓を現代の組織運営や個人の成長にどう活かせるかを解説します。
「烏合の衆」の出典と意味
後漢末期の騒乱期、反乱軍が統率を欠いたまま徒党を組んで略奪を行い、それを形容する際に「烏合」(うごう)という言葉が使われました。「烏」は群れる習性を持ちながらも秩序を欠くカラスの姿に例えられています。
規律がなく、ただ寄り集まっているだけの群衆
「後漢書」耿弇伝
歴史的な背景
出典先の『後漢書』では、烏合の衆が「カラスがただ群れ集まるように、何のまとまりもない集団」という形で記されています。この記述は、群衆が目的や方向性を共有しておらず、ただ漫然と存在している様子を象徴的に表しています。
「烏合の衆」の現代的解釈
「烏合の衆」とは、下記の特徴を持つ人々の集まりを表現する際に使われます。
- 明確な目標や方向性がない
- 統率力を欠いている
- 個々がバラバラに行動し、協調性がない
現代に置き換えますと、組織内でリーダーシップ不足や目標の不明確さにより効率性を欠く状況を指すこともあります。
リーダーシップと統率力の重要性
この故事から得られる教訓を以下に挙げます:
1. 目的とビジョンを共有することの重要性
組織またはチームが同じ目標・価値を共有し、目的に向かって一丸となることが必要です。優れたリーダーシップを発揮していると思われる企業を下記に挙げてみます。
- リクルートホールディングス
リクルートは、ビジョン「すべての企業活動を通じて、持続可能で豊かな社会に貢献する」を掲げています。一人ひとりの好奇心を重視し、それを原動力に新しい価値を創造する文化を醸成しています。 - 富士フイルム株式会社
富士フイルムは中期経営計画「VISION 2023」を通じ、ヘルスケアや高機能材料の成長を加速させるとともに、持続可能な事業基盤の構築を目指しています。このように具体的な目標を設定し、全社で共有することで成長を支えています。 - 良品計画(無印良品)
良品計画は「日常生活の基本を担う」「地域への土着化」というビジョンを掲げ、地域密着型の事業モデルを構築しています。また、全社員が自発的に活動する組織文化を目指し、社員がビジョンに共感する仕組みを作っています。 - シナジーマーケティング株式会社
「人と企業が惹かれ合う世の中へ」というビジョンを中心に、顧客との強い関係を築くサービスを展開しています。具体的な行動指針を「101点のサービス」として表現し、社員全体に浸透させています。 - Amazon.com 「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」をビジョンに掲げて顧客利益を重視したサービスを展開しています。従業員にはアルバイトのL1、契約社員のL2〜3、L4〜L10といったステータスが年齢、性別、障がいなどのハンディキャップ不問で成長する機会をうたっています。
- 上記に挙げた企業は、目的やビジョンを掲げるだけでなく、具体的な行動指針や計画に落とし込むことで、社員全体に共有・浸透させています。
- 社員が自分の役割をビジョンに結びつけられるよう、ワークショップやリーダーの育成なども実施しています。
2. リーダーシップの欠落とその傾向
組織をまとめ、正しい方向性を示すリーダーがいない場合、個々の能力が高くても成果を上げることは難しいです。下記に、主な問題の傾向を挙げてみます。
a. 意思決定の遅延によるパフォーマンス低下
リーダーが明確な方向性を示せない組織では、意思決定が分散し、迅速な対応が求められる状況で行動が遅れる場合があります。例えば、ある企業が複数の部門で意見を調整しようとした際にリーダーシップが欠けていたため、製品の市場投入が大幅に遅れたケースがあります。このような遅延は競争環境での優位性を失わせる原因になります。
b. 部門間の連携の弱体化
部門間のつながりが希薄な状況では、技術者と営業担当者が日常的にコミュニケーションを取らず、顧客ニーズを正確に反映できない製品開発に陥ることがあります。リーダーによっては、こうした断絶を埋め、チーム全体が共通目標に向かうことが可能ですが、リーダー不在では部門間の対立や無関心が生じる可能性があります。
c. モチベーションの低下と人材流出
リーダーシップが不足している職場では、社員のモチベーションが低下し、優秀な人材が組織を離れることがあります。例えば、ビジョンを共有できず目標が不明確な場合、社員は自己成長ややりがいを感じにくくなり、結果として転職を選ぶケースが多く見られます。
3. 連携と協調性
a. 役割分担と責任の明確化
ポジティブな傾向:各メンバーの役割や責任が明確であると、チーム内で効率的に連携できるようになります。役割が明確であることは、タスクの重複を防ぎ、リソースを最大限に活用するのに役立ちます。
ネガティブな傾向:役割が曖昧な場合、メンバー各自がその役割を理解できず、業務の遅延や責任逃れが発生する可能性があります
b. コミュニケーションの質
ポジティブな傾向:開かれたコミュニケーションが実現できるチームでは、意見交換やフィードバックが活発になり、協調性が向上します。これにより問題解決が迅速に行われ、チームの士気が高まります。
ネガティブな傾向:目標が不明確であったり、メンバー間で意見の相違がある場合、目指す方向性が分散し、チームとしての機能が低下します。
c. リーダーシップの存在
ポジティブな傾向:明確なリーダーが存在する場合、適格な方向性を示し、メンバー間の連携を調整する役割を果たします。リーダーが連携のブリッジ(橋渡し役)を担うことで、協調性が一層高まります。
ネガティブな傾向:リーダーが不在、またはリーダーシップが弱い場合、意見が分裂したり、連携が効果的に行われない場合があります。
ビジネスの教訓
- 統率力の欠如は失敗を招く:無秩序・無規律な組織・集団は、個々の能力が高くても成果を上げることができません。
- 明確な目標設定が必要:全員が同じ方向を向いて進むためには、目標を明確にすることが不可欠です。
- リーダーの存在:リーダーは集団をまとめ上げ、適切な指示を出し、全体の調和を図る役割を果たします。

田中部長と烏合の衆 ~営業部、バラバラからの逆襲!?~
月初の営業部ミーティング。しかし、目標が共有されないままメンバーはそれぞれ勝手な方向に意見を出し合い、会議は収拾がつかない状態になっていた…。
【登場人物】
- 田中部長(50歳):リーダーとしての威厳を保とうとするが、方向性を見失いがちな部長。
- 山本課長(40歳):冷静沈着で現実主義者。会議が混乱するとすかさずツッコむ頼れる皮肉屋。
- 佐藤さん(25歳):天然で自由奔放。結果的にいつも話をややこしくするムードメーカー。
【会話】
田中部長:「みんな、今月の目標について話し合おう!まずはアイデアを出してくれ!」
佐藤さん:「はい!私、ノベルティを配るキャンペーンがいいと思います!」
山本課長:「いや、それ予算オーバーで無理ですよ。むしろリピート顧客向けのアップセルを考えるべきです。」
佐藤さん:「ええー、それじゃ地味すぎませんか?もっと派手にやりましょうよ!」
田中部長:「落ち着け!まだ始まったばかりだぞ!他に意見は?」
佐藤さん:「じゃあ、SNSで『営業部の田中部長が踊る動画』を配信するのはどうですか?」
山本課長:「佐藤さん、それは論外です。」
田中部長:「おい、佐藤くん!君、私をなんだと思っているんだ!」
佐藤さん:「営業部のスターですよ!」
山本課長:「スターじゃなくて、バラエティタレント扱いですよね。」
田中部長:「むむむ…こうしてみんながバラバラなことを言うから、まとまらないんだ!」
佐藤さん:「じゃあ部長、どうやって決めるんですか?」
田中部長:「…こうなったら、われわれ営業部が“烏合の衆”になっている理由を見直さなければならん!」
【田中部長、突然の「烏合の衆」講座】
田中部長:「いいか、烏合の衆という言葉を知っているか?」
佐藤さん:「聞いたことはありますけど…カラスが集まってる、ってことですよね?」
山本課長:「正確には、まとまりがなくて秩序がない集団を指します。つまり、われわれのことです。」
田中部長:「その通りだ!だが、烏合の衆にも可能性がある!」
佐藤さん:「可能性…ですか?」
田中部長:「そうだ!カラスだって、上手く連携すれば素晴らしいチームになる!」
山本課長:「いや、部長。カラスの話じゃなくて、営業戦略を話しましょうよ。」
田中部長:「うるさい!いいか、カラスには“仲間の危険を知らせる”習性があるんだ。つまり、情報共有を徹底すれば烏合の衆も立派な組織になる!」
佐藤さん:「じゃあ、営業部もカラスみたいに鳴き声で連絡しあえばいいんですか?」
田中部長:「…それは違う!」
山本課長:「部長、何が言いたいんですか?要するに、我々もチームワークを鍛えろと?」
田中部長:「そうだ!まずは全員が同じ方向を向くことが大事だ!そのためには…」
【営業部、チームワーク改善特訓】
(数日後、田中部長が企画した「烏合の衆を脱却するワークショップ」が開催される)
田中部長:「では、今から“カラスのように情報を共有する訓練”を始める!」
佐藤さん:「部長、それどうやってやるんですか?」
田中部長:「簡単だ!みんなで円になって、一人ずつ今の営業目標を“カラスの鳴き声風”に伝えるんだ!」
山本課長:「……部長、本気ですか?」
田中部長:「真剣だ!営業とは時に遊び心も必要なんだ!」
(佐藤さん、ノリノリで「カーカー!」と目標を発表)
佐藤さん:「次は山本課長ですよ!」
山本課長:「…俺、何やってるんだろう。」
田中部長:「いいぞ!こうして全員が声を合わせれば、烏合の衆から立派な“営業部”へと進化できる!」
こうして、田中部長の“烏合の衆”脱却計画は、謎のカラス訓練によって幕を閉じた。その効果は不明だが、営業部の絆は少しだけ深まった。
まとめ
「烏合の衆」という故事は、組織や集団が統率力を欠いた時に起こりうる危険を私たちに警告しています。現代のビジネスシーンにおいても、明確なビジョンを共有し、リーダーシップを発揮することで、どんなチームも烏合の衆ではなく、成功に向かう「有機的」な組織・集団となることができます。
統率を意識した組織づくりこそが、ビジネスの成功を引き寄せる鍵なのです。