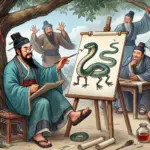出典:世説新語
はじめに
中国の「世説新語(せせつしんご)」は、南北朝時代の劉義慶(りゅうぎけい)によって編纂された、魏晋南北朝期(3~6世紀頃)の逸話や人物評を収録した文学作品です。その中には、多くの人物にまつわるエピソードが収められており、士大夫階級(知識人・官僚層)の言動や風采、機知に富んだ逸話が数多く記録されています。その中でも有名なものの一つとして、「青眼(せいがん)」と「白眼(はくがん)」を使い分けたことで知られる、阮籍(げんせき)にまつわる逸話があります。
白眼視とは
冷たい目で見ること、見られることを指します。
竹林の七賢の一人・阮籍は、自分が気に入った人物や尊敬に値する人物に対しては“青眼”で見つめ、逆に受け入れがたい人物や軽蔑する人物に対しては“白眼”で見たといわれます。
- 青眼:瞳孔を相手に向け、好意・敬意・友情などを示す視線。瞳が黒々としている様子が青みがかって見えることから「青眼」と称されたとされます。
- 白眼:瞼(まぶた)や白目の部分だけを相手に向け、相手を拒絶・軽蔑する意を示す視線。
もともと東洋医学などでも、白目と黒目の対比が人の感情や体調を映し出す要素として捉えられていました。阮籍の逸話は、その「眼差し」による好悪の表現が、直接相手に「好き」「嫌い」を突きつける率直さとして後世に広く知られるようになったものです。
「白眼視」のエピソード
具体的には、「世説新語」の「容止(ようし)」や「任誕(にんたん)」の章に阮籍の奇行が取り上げられており、そこには次のようなエピソードが残っています。
ある日、阮籍が訪問客を応対していたとき、好ましいと思う人に対しては瞳をしっかり相手へ向け、「青眼」で丁寧に応じました。しかし、訪問してきた客の中に彼が嫌悪する人物がいた際には、一瞬たりとも瞳を合わせず、白目だけを向ける「白眼」で応対しました。これは明らかな拒絶や軽蔑の意思表示であり、当時の礼儀が重んじられる社会においては相当際立った行為でもありました。
このように、阮籍の「白眼」は単なる見下しの態度を表すだけでなく、当時の社会のしがらみに囚われず、内心の感情をあからさまに示す彼の奔放な個性を象徴するエピソードとして伝わっています。
「白眼視」の意味と後世への影響
日本語の慣用表現にも、「白い目で見る」「白眼視する」という形で残っており、これは相手を冷淡・軽蔑・拒絶の念を込めて見ることを指します。現代でも、人や行為を否定的に捉えるとき、「あの人に白い目で見られた」「世間の白い目を浴びる」などと表現されるのは、この故事が出典とされています。
また、この「白眼」「青眼」の使い分けは、中国においては当時の清談(せいだん)文化の象徴でもありました。清談とは、老荘思想などを背景にした哲学的・機知的な談義で、魏晋期の知識人たちが現実の政治や儀礼を嫌い、自由闊達に議論を楽しんだ文化です。阮籍や嵆康(けいこう)をはじめとする竹林の七賢は、この清談文化の中心的人物であり、彼らの生き様や逸話は、その後の文人・知識人層の精神的支柱や理想とされました。
「白眼視」の物語が持つメッセージ
阮籍の「白眼視」は、一見すると相手を軽んじる傲慢な態度にも思えますが、その背景には、当時の権力争いが激化する政治社会に対する批判や、権勢や儀礼的形式ばかりを重んじる人物への嫌悪感もあったとされています。彼の行動には、社会の通念や体裁よりも、内面的な価値観や率直な感情を優先するという魏晋の士人たちの思想的背景がうかがえます。
後世、魏晋風流を理想化した人々や、世俗の価値観に反発する人々にとっては、このエピソードこそが自我の表明や自由の象徴となりました。阮籍の「白眼視」は、社会のしがらみにとらわれずに生きる気概や、時には反体制的な精神までも感じさせるものとして、多くの文人たちの共感を呼び、文学や詩歌などにも大きな影響を与えていきます。
ビジネスシーン: 冷ややかな態度の意味とは?
【登場人物】
- 田中部長: 部下の行動を観察し、時折冷静に指導を入れるベテランリーダー。
- 山本課長: 行動派だが、時に空気を読まずに突っ走るタイプ。
- 佐藤さん: 観察力が高く、時折鋭いツッコミを入れる新人社員。
舞台は営業部のオフィス。新しいクライアントとの打ち合わせが終わり、反省会をしている場面から始まる。
田中部長:
「さて、今日の打ち合わせについて振り返ろうか。まずは山本、君から意見を聞こう。」
山本課長:
「はい!クライアントへの提案、なかなか良かったと思います。特に、ボクが熱弁を振るった部分は、きっと響いたと思います!」
佐藤さん:
「課長……その熱弁の最中、クライアントが微妙な顔をしていたのを気づいてました?」
山本課長:
「え?微妙な顔?そんなことなかったでしょ!むしろ感心してたんじゃない?」
佐藤さん:
「いや、完全に『白眼視』されてましたよ。」
山本課長:
「『白眼視』って何だ?」
田中部長:
「佐藤、君の指摘は鋭いな。『白眼視』の話をするのにちょうどいいタイミングだ。」
【故事の解説】
田中部長:
「『白眼視』とは、中国の『世説新語』に出てくる故事から来ている。魏晋南北朝時代の名士、阮籍(げんせき)は、人に対して感情をあらわにしない態度で有名だった。」
佐藤さん:
「阮籍って、気に入った相手には黒目を向け、嫌いな相手には白目を向けた人ですよね?」
田中部長:
「そうだ。彼は、相手に対して冷淡な態度を示すとき、わざと白目を見せて接した。これが後に『白眼視』として、『軽蔑や冷ややかな視線』を意味するようになった。」
山本課長:
「つまり、今日のクライアントが僕に冷ややかな視線を送っていたってこと?」
佐藤さん:
「はい。特に、課長が提案の話を脱線して自慢話を始めたとき、完全に白目状態でした(笑)。」
【白眼視の原因を分析】
山本課長:
「でも、僕は良かれと思って話してたんだ!どうしてそんな態度を取られたんだろう……。」
田中部長:
「山本、相手の反応をよく観察することが大事だ。クライアントが何を求めているのかを見極める前に、熱弁を振るったり、自分の話を押し付けると、白眼視される原因になる。」
佐藤さん:
「課長、クライアントは具体的な解決策を求めていましたよね。それに答えられないと、ただの自己アピールに聞こえてしまうこともあるんです。」
【改善策を考える】
山本課長:
「なるほど……自分の話ばかりで、クライアントのニーズをちゃんと考えられていなかったかも。」
田中部長:
「そうだな。『白眼視』を受けるのは、相手の期待に応えられていない証拠だ。次回はクライアントの話をしっかり聞き、相手にとって価値のある提案をすることを心がけよう。」
佐藤さん:
「課長、次回は『黒目視』を目指しましょう!つまり、相手から信頼の眼差しを向けられるように!」
山本課長:
「わかった!今度は相手の反応をよく見て、空気を読んだ発言をするようにするよ。」
【結果】(数週間後)
佐藤さん:
「部長、課長、今回の打ち合わせ、大成功でしたね!クライアントからも笑顔で感謝の言葉をもらえました!」
山本課長:
「おかげで、今回は『白眼視』どころか、『目を輝かせて』聞いてもらえたよ!」
田中部長:
「素晴らしい。相手の期待に応えることで、信頼を築くことができたな。これからも、相手の視線の意味を理解しながら行動していこう。」
佐藤さん:
「はい!次回も相手に喜ばれる提案を目指します!」
【教訓】
「白眼視」の教えは、相手の態度や視線が自分の行動の反映であることを示しています。ビジネスや日常においても、相手の期待や感情に敏感に対応することで、信頼を得ることができます。冷ややかな視線を避け、温かな信頼を築くためには、相手をよく観察し、適切な行動を取ることが大切です。
まとめ
「白眼視」という表現は、日常生活でもしばしば聞かれるほど広く定着しています。そのルーツとなった「世説新語」の逸話は、単なる軽蔑の眼差しというだけでなく、魏晋南北朝の知識人たちが持っていた自由闊達な精神と、世俗への批判精神を象徴する物語でもあります。
阮籍のように、「白眼」「青眼」を使い分けることで自分の本音を明確に示す姿は、現代の私たちにとっても示唆に富むものです。社会のルールや慣習、周囲の視線を過度に気にしすぎて自分の価値観を見失いがちなとき、あえて自分の感情に素直であることの大切さを思い出させてくれる物語と言えるでしょう。