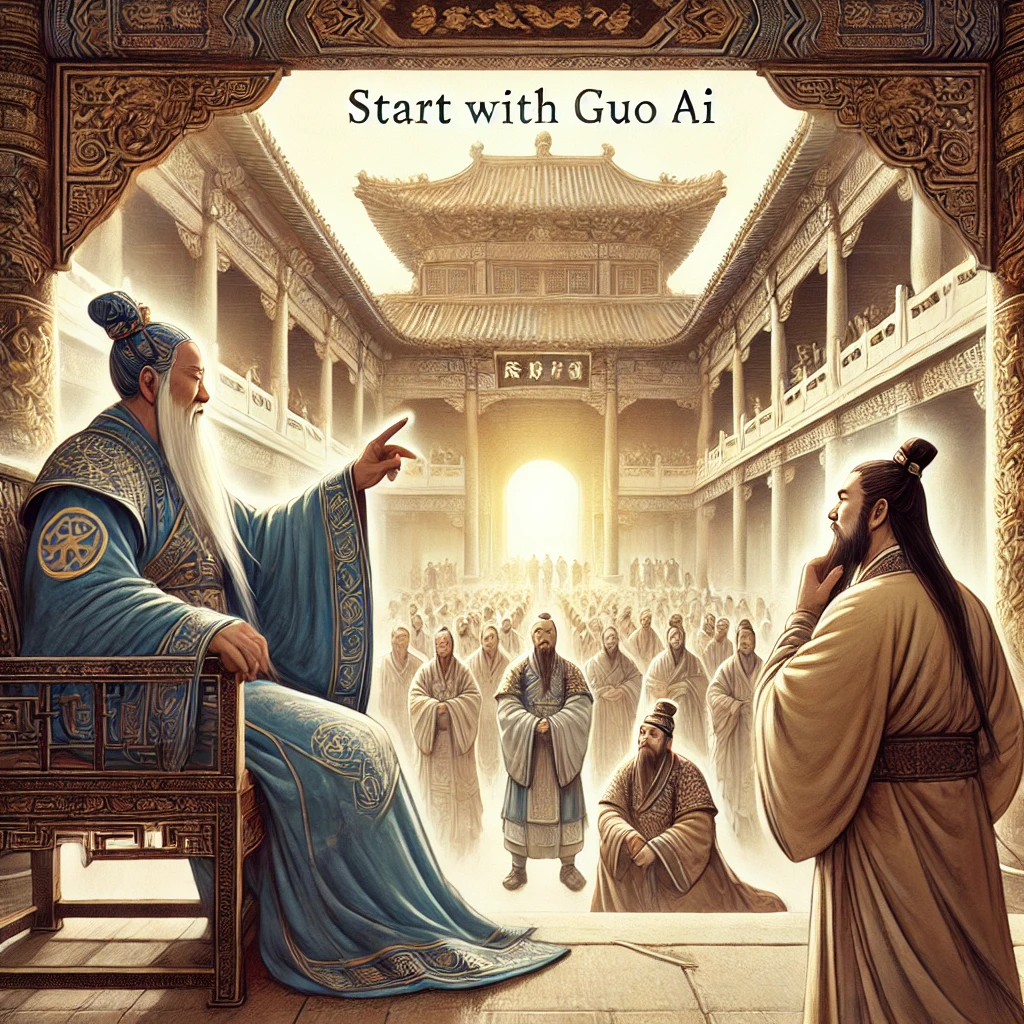出典:戦国策
「先ず隗より始めよ」とは「先ず隗より始めよ」「先ず隗より始めよ」とは
「先ず隗より始めよ」(まずかいよりはじめよ)とは、中国の戦国時代に由来する言葉で、「大きな目標を達成するためには、まず身近なところから始めることが大切だ」という意味を持ちます。
この故事が表す具体的なエピソードは、王や指導者が“優秀な人材を集めよう”と考えたとき、最初に自分自身や身近な存在を登用することで、周囲の優秀な人たちを惹きつけるという考え方です。
本来は「有能な人材を呼び込むなら、まず身近な人物を大切にせよ」という文脈で語られます。しかし現代では、もっと広い意味で「大きな計画・試みを始めたいときは、まず取り組みやすいところから着手しよう」という解釈で使われることも多いです。
- 大きなことを成し遂げるには、まず自分の足元をしっかり固める
- 周囲に“やる気”や“本気度”を伝えることで、賛同者が自然と集まってくる
「先ず隗より始めよ」の由来
1. 戦国時代の背景
中国の戦国時代(紀元前5世紀ごろ〜紀元前3世紀ごろ)は、各国が覇権を争った混乱の時代。各国の王たちは有能な人材を求めて、思想家や将軍を招聘し、国力を高めることにしのぎを削っていました。
2. 燕王(えんおう)と郭隗(かくかい)
「先ず隗より始めよ」の故事は、戦国時代の燕(えん)という国の王と、郭隗という人物のやり取りに由来します。
燕王が優秀な人材を集めたい
燕王は、燕の国力を蓄えるために「天下の優れた人材を我が国に招きたいが、どうすれば良いだろうか?」と臣下たちに問いかけました。
郭隗の進言
これに対して郭隗が「王様が本気で優秀な人材を求めるなら、まずは私のような者を重用してみてください。私が王から非常な厚遇を受けていると知れば、私よりも優秀な人材は必ずや集まってくるでしょう」と提案しました。
王が実行し、優秀な人材が集う
燕王は郭隗の進言どおり、まず郭隗を高い地位につけて礼遇しました。それを見た多くの才能ある人々が燕に集い、燕王の国は大いに力を得ました。
現代社会への応用
1.ビジネスや組織運営
たとえば、新規事業を立ち上げたり、大胆な改革を進めたりするとき、「まず隗より始めよ」の精神が活きてきます。社長やリーダー自身が率先して、近しい仲間や部下を手厚く育成し、実績を作ることで外部の優秀な人材が引き寄せられる――という流れが起こりやすくなります。
2. プロジェクトのチームビルディング
何か新しいプロジェクトを立ち上げるときも同様です。いきなり外部から大物を呼び込むのではなく、チーム内で才能を見いだして活用することで、プロジェクトが軌道に乗り、評判が高まれば、後から優秀な人材が加わってくれるかもしれません。
3. 個人の成長戦略
個人レベルでも、遠くにある大きな目標だけを見ていても、行動に移さなければ周囲の協力者や情報は集まりません。まず身近なこと(たとえば自分のスキルアップや小さな挑戦)に注力する姿勢が、周りの信頼を得て、大きなチャンスにつながります。
まとめ
「先ず隗より始めよ」は、「大きな野心や夢があるなら、まずは身近な人や自分自身を大切に扱い、信頼を得よう」というメッセージを現代人に伝えてくれます。壮大なプランを描くのは大切ですが、それを実現するためには、まず動き出すための土台や、周囲の共感が必要です。

田中部長と「先ず隗より始めよ」~営業部、まずは自分から!?~
ある日、営業部に 「新規プロジェクトのリーダーを決める」 という重要なミッションが降りてきた。しかし、田中部長が 「まずは自分がやる!」 という方針を打ち出し、営業部は大混乱に――!?
【登場人物】
- 田中部長(50歳):自ら手本を示すと言いながら、なぜか周囲を巻き込む熱血リーダー。
- 山本課長(40歳):現実主義のツッコミ担当。部長の暴走を止めるのが日課。
- 佐藤さん(25歳):天然で無邪気。部長の方針を素直に受け取り、余計な行動をしてしまう。
田中部長:「みんな!この営業部にとって、歴史に残るプロジェクトが始まる!」
佐藤さん:「ええっ!?そんなにすごいプロジェクトなんですか?」
山本課長:「また部長が大げさに言ってるだけじゃないですか?」
田中部長:「今回は本当にすごい!新規クライアント開拓プロジェクトだ!」
佐藤さん:「わあ!新規クライアントってことは、私たちがどんどん新しい会社にアプローチするんですね!」
田中部長:「その通り!だが、そのためには“リーダー”が必要だ!」
山本課長:「またリーダー決めですか…。部長、ちゃんと適材適所で選びましょうよ。」
田中部長:「いや、ここで重要なのは“先ず隗より始めよ”の精神だ!」
佐藤さん:「えっ?なんですか、それ?」
山本課長:「これは、“大きなことを成し遂げるには、まず身近なところから始めるべき”っていう故事ですよ。」
田中部長:「そうだ!だからリーダーは… まずはこの私がやる!!」
佐藤さん:「おおお!!さすが部長!」
山本課長:「いや、そもそも部長はいつもリーダーですよね?」
【田中部長の「先ず隗より始めよ」作戦】
作戦①:まずは自分が飛び込み営業!
田中部長:「まずは私が“営業の見本”を見せる!飛び込み営業だ!」
佐藤さん:「えっ!?今どき飛び込み営業なんですか?」
山本課長:「いや、今の時代、アポなしで行ったら普通に断られますよ。」
田中部長:「いや、直接顔を見せることが大事なんだ!見ていろ!」
(数分後、近所のオフィスへ突撃し、5分で戻ってくる)
佐藤さん:「どうでした?」
田中部長:「門前払いだった!」
山本課長:「ほら言わんこっちゃない。」
作戦②:「まずは自分から」スローガンを掲げる
田中部長:「次だ!営業部全員の意識を高めるため、“まずは自分から!”のスローガンを掲げる!」
佐藤さん:「えっ?どういうことですか?」
田中部長:「例えば、仕事の改善提案があるなら『誰かやってくれ』じゃなく、まず自分がやる!そういう意識改革だ!」
山本課長:「いや、それ普通に“主体性を持つ”ってことですよね?」
佐藤さん:「じゃあ、まずは私、会議室を全力で掃除します!」
山本課長:「いや、掃除より先に営業の提案を考えましょうよ。」
(佐藤さん、突然モップを持って猛ダッシュ)
作戦③:「部長が見本」と言ったのに、なぜか部下がやることに
田中部長:「そして、最終的には私が“新規営業のマニュアル”を作る!」
佐藤さん:「おおお!!すごい!」
山本課長:「いや、それはありがたいですけど、部長がやるって言って、また途中で私に投げません?」
田中部長:「そんなことはない!今度こそやり遂げる!」
(30分後――)
田中部長:「うむ…やっぱりこれは“部下が学ぶ機会”を作るべきだな!」
山本課長:「ほらやっぱり!!」
佐藤さん:「じゃあ、私がマニュアル作ります!」
田中部長:「よし!佐藤くん、任せた!」
山本課長:「結局、最初に決めた“部長がやる”って話はどこに行ったんですか?」
【商談当日:まさかの展開】
(営業部が新規クライアントとの初回商談へ)
クライアント:「本日はよろしくお願いします。」
田中部長:「こちらこそよろしくお願いします!我々は“先ず隗より始めよ”の精神で営業活動を行っています!」
クライアント:「えっ?どういうことですか?」
佐藤さん:「つまり、まずは部長が自ら営業活動をして、部下にも主体性を持たせるという…」
山本課長(小声で):「実際には途中で部下に投げてるけどな…。」
クライアント:「なるほど!自ら率先して動く姿勢は、我々の会社の方針と合致しますね。」
佐藤さん:「えっ!?本当に?」
クライアント:「ぜひ、次回の提案もお願いしたいです。」
山本課長(小声で):「まさかこんな理屈が通るとは…。」
田中部長:「見たか!これが“先ず隗より始めよ”営業だ!」
山本課長:「いや、もう少し普通にやってください。」
こうして営業部は、田中部長の “まず自分がやる!” という無謀な方針の中、なんとか契約を勝ち取ることに成功した。しかし、その方法が次回も通用するかは未知数であり、彼らのドタバタは続くのであった――。