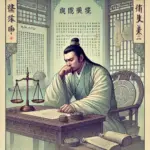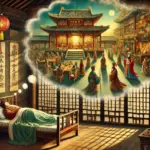出典:韓非子
矛盾とは
「矛盾」は、中国の古代思想を学ぶ上でよく知られた故事成句で、物事の対立や論理の自己矛盾を象徴する表現として現代でも幅広く用いられています。
この故事は古代中国の『韓非子』(かんぴし)という法家思想の著作に収められており、「難一篇」に掲載されています。法家の思想家・韓非は、言葉や行動が矛盾する人々の様子を鋭く批判する際に、このエピソードを引き合いに出しました。
「矛盾」の逸話
古代中国の楚国に一人の商人がいました。この商人は、武器を売ることを生業としており、市場で自分の武器の優れた特性を誇らしげに宣伝していました。ある日、商人は見物人たちに向かって、手に持つ矛(ほこ)を示しながらこう言いました。「この矛は、何でも突き通すことができる最強の矛です!」と。
彼の言葉は堂々としており、自信に満ち溢れていました。
しかし、次の瞬間、商人は同じように手に持つ盾を示して、「この盾は、どんな攻撃も防ぎきることができる最強の盾です!」と主張しました。
どんな矛の攻撃でも決して貫通されないというこの盾の特性に、周囲の人々は驚きと感心の声を上げました。‘しかし、すぐにその場にいた一人の見物人が商人に問いかけました。「あなたの矛であなたの盾を突いたら、どうなるのですか?」
この単純ながら鋭い質問に、商人は言葉を失い、何も答えられませんでした。このエピソードが由来となり、「矛盾」という言葉は「二つのことにつじつまが合わない」という意味で使われるようになりました。
商人が自ら主張した二つの特性が互いに相反することで、自分自身が矛盾を引き起こしてしまった様子が、見事に物語られています。
歴史的背景と教訓
この逸話が登場する『韓非子』は、戦国時代(紀元前5世紀から紀元前3世紀)の中国における思想書で、当時の複雑な社会情勢や権力争いを背景に、法と秩序を重視する法家(ほうか)を示したものです。韓非は、言葉の矛盾や不合理を批判し、物事を合理的かつ現実的に捉えるべきだと説いていました。
「矛盾」の逸話は、理屈に合わないことが起きる状況や、人間の言動の裏表を見抜く視点を与えてくれます。
なお、諸葛孔明は韓非子を愛読していて、「泣いて馬謖を斬る」は、その影響を強く受けています。
現代における「矛盾」の応用
この逸話の教訓は、現代ビジネスや人間関係にも活かすことができます。例えば、企業や個人が何かを宣言したり行動したりする際に、その言葉や行動が一貫性を持つことが求められます。信頼や信用を築くには、矛盾しない行動を示すことが大切であり、その重要性を教えてくれます。また、論理的な思考を必要とする場面では、「矛盾」を指摘し、問題を整理することで解決の糸口を見つけることも可能です。
「矛盾」とは、深い教訓を含むものとして長い歴史の中で語り継がれてきました。自らの言葉や行動が一貫性を持っているかを見つめ直し、現代社会においても人々の思考を研ぎ澄ませる助けとなるでしょう。

両立しないPRの愚かさを考えた商品広報
【登場人物】
- 田中部長: チーム全体を見守り、論理的な指摘が得意なリーダー。
- 山本課長: 熱意に溢れる行動派だが、時に話が矛盾することがある。
- 佐藤さん: 素直で観察力が高い新人社員。鋭いツッコミが得意。
舞台は営業部の会議室。新しい商品の特長について話し合い中。山本課長が勢いよく意見を述べる。
山本課長:
「今回の新商品、『無敵ガードマスク』ですが、最高の売り文句はこれですよ!『どんなウイルスも通さない最強の防御力!』そして、『通気性抜群で息がしやすい!』これで完璧です!」
佐藤さん:
「……課長、それってちょっと矛盾していませんか?」
山本課長:
「矛盾?いやいや、どちらも事実ですよ!防御力が高くて、息もしやすい。これぞ理想のマスクです!」
田中部長:
「山本、それを聞いて思い出すのが故事の『矛盾』だな。」
山本課長:
「え、『矛盾』ってどんな話なんですか?」
【故事の解説】
田中部長:
「昔、中国のある商人が『この矛はどんな盾でも貫く』と宣伝し、次に『この盾はどんな矛も防ぐ』と売り始めた。」
佐藤さん:
「……その2つを同時に売ったんですか?」
田中部長:
「そうだ。お客さんが『じゃあ、その矛でその盾を突いたらどうなる?』と聞くと、商人は答えに詰まってしまった。それ以来、両立しない主張を『矛盾』と言うようになったんだ。」
山本課長:
「なるほど……でも、それと今回のマスクの話はちょっと違うんじゃないですか?」
【矛盾の指摘】
佐藤さん:
「課長、通気性が良いってことは空気が通るってことですよね?それって、ウイルスも通るんじゃ……?」
山本課長:
「……うっ、それは……。いや、最新技術で、空気は通すけどウイルスは通さないフィルターがあるんだよ!」
田中部長:
「その理屈が本当に成立しているなら問題ない。だが、技術の限界を過剰に期待させる説明は、顧客の信頼を損ねる可能性がある。」
佐藤さん:
「たしかに。誇大広告みたいになっちゃうと、逆効果ですよね。」
【矛盾を回避する議論】
山本課長:
「でも、売り文句って強烈な方がインパクトがあるじゃないですか!地味だと目立たないし……。」
田中部長:
「目立つことは大事だが、矛盾を生む主張は信用を失う。顧客が感じる矛盾を解消する説明が必要だ。」
佐藤さん:
「例えば、『快適な通気性と防御力を両立するバランス設計』みたいな言い方にすると、矛盾を感じにくくなるかもしれません!」
山本課長:
「それだ!完璧じゃなくても、十分納得してもらえる表現になる!」
【結果】
(数週間後)
佐藤さん:
「部長、新しい広告が好評です!お客様からも『納得感がある説明』と褒められました。」
山本課長:
「確かに、佐藤の案を採用してよかったよ。あのまま矛盾したままだと炎上してたかもしれないな(笑)。」
田中部長:
「その通りだ。『矛盾』は論理の落とし穴だが、それを克服すれば信頼を得られる。今回の学びを次にも活かしていこう。」
佐藤さん:
「はい!矛盾に気をつけて、誠実な仕事を心がけます!」
【教訓】
「矛盾」の教えは、論理が破綻している主張は、どんなに魅力的でも信用を失う原因になるというものです。ビジネスや日常においても、相手が納得できる説明を心がけ、誠実に事実を伝えることで、信頼を築くことが大切です。