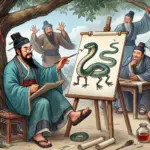出典:詩話総亀
「推敲(すいこう)」とは
「推敲(すいこう)」とは、詩や文章を練り直して完成度を高めることを指します。この言葉の由来は、唐代の詩人・賈島(かとう)が、自作の詩を作る際に「推す(押す)」と「敲く(たたく)」のどちらの表現を用いるべきか迷い、試行錯誤した故事から来ています。この逸話は、文章や作品に対してこだわりを持ち、細部まで磨きをかけることを言います。つまり、文字を書いた後、表現を良くするために何回も読み返して文章を練り直すことです。
「推敲」の時代背景
唐代(618年–907年)は、文化と芸術が隆盛を極めた時代でした。この時代、詩作は文人の重要な活動の一つであり、優れた詩は名声と地位をもたらしました。そのため、詩人たちは一語一句に細心の注意を払い、作品を練り上げることに力を注ぎました。賈島はその代表的な詩人の一人です。また、
エピソード
賈島が科挙の試験に長安に向かっているとき、彼はロバの背のうえで、詩を詠んでいました。
鸟宿池边树, 僧敲月下门鳥
(鳥は池のほとりの木で眠り、僧は月の下で戸をたたく)
最初は 「僧推月下門(僧は月下の門を押す)」の「おす(推)」で表現をしたかったのですが、「たたく(敲)」がふさわしいと、賈島は思いました。ところが、いくたびか考えてもまだ決まらず、ロバの背の上で、手を伸ばして「おす」「たたく」と、感情を込めて動作を繰り返し、詩を詠み続けました。
すると、長安の都督・韩愈が馬車を連ねて演説している場所を通り過ぎていきました。
ところが、賈島はその演説と聴衆にまったく気が付かずに、素通りしながら「押す」「たたく」の仕草を繰り返して通り過ぎました。
すると、賈島が乗るロバが、誤って韩愈の従者にぶつかってしまいました。
韩愈の従者は、無礼な賈島を捕らえて、韩愈の面前に連れ出しました。
すると、賈島は自分が悩んでいたことを詳しく説明しました。つまり、「おす」「たたく」のどちらがふさわしいか悩み、目の前のことが頭から離れてしまい、なにを避けるべきであったか、わからなかったというのです。
それを聞いた韩愈はしばらく考えました。
そして、韩愈は賈島に自分の考えを伝えました。
『「たたく」がよい。月下に音の響きがあってふさわしい』
韩愈は怒るどころか、賈島の詩の完成を手助けしました。
それを聞いた賈島は、大いに喜び、感嘆しました。
韩愈と賈島は意気投合して、ともに詩を詠みながら家路につきました。
それから、二人はお互いに離れがたく、数日間一緒に旅をしたのだそうです。
この話が「推敲」の語源とされています。
現代社会での教訓と応用
「推敲」は、現代においても、特にビジネスや創作活動で重要な意味を持ちます。下記のような教訓が得られます。
成果物の品質を高めるための試行錯誤
文章やデザインの校正や戦略の練り直しは、価値ある成果物を生むために欠かせません。焦らずに手直しを繰り返すことで、完成度の高い結果が得られます。
フィードバックを受け入れる姿勢
韓愈が賈島の詩に助言をしたように、他者からの意見や視点を受け入れることで、自己の考えや表現をより豊かにできます。
プロフェッショナリズム
どんな分野でも、仕事や創作において細部にまでこだわる姿勢がプロフェッショナルを作り出します。

田中部長と推敲 ~営業部、完璧を目指して空回り!?~
今月の大型商談に向けた提案書を作成している営業部。しかし、田中部長が「完璧な提案書」を求めるあまり、いつまで経っても内容が決まらないという状況に…。
【登場人物】
- 田中部長(50歳):完璧主義だが、細部にこだわりすぎてよく空回りするリーダー。
- 山本課長(40歳):現実主義者で効率重視。部長の「推敲地獄」に巻き込まれる皮肉屋。
- 佐藤さん(25歳):素直で無邪気だが、提案書作成でトラブルメーカーになる新人。
田中部長:「みんな!今回の大型商談は、営業部の未来を左右する重要な案件だ!」
佐藤さん:「はい!提案書はもう90%完成してます!」
山本課長:「そうですね。あとは細かい修正をして、明日にはクライアントに提出できるかと。」
田中部長:「待て!“90%”ではダメだ!商談に勝つには、完璧な提案書が必要だ!」
佐藤さん:「でも、ほとんど完成してますよ?あと何を直せばいいんですか?」
田中部長:「いいか、佐藤くん。“推敲”という言葉を知っているか?」
佐藤さん:「えっと…聞いたことはありますけど、詳しくはわかりません。」
山本課長:「推敲って、文章を何度も見直して、より良い表現を探すことですよね。」
田中部長:「その通りだ!これは唐の詩人、賈島が詩を書いた時の話に由来する。“僧は門を叩く(推)”とするか、“僧は門を敲く(敲)”とするかで悩んだんだ!」
佐藤さん:「なるほど…。でも、それって今の提案書にどう関係するんですか?」
田中部長:「提案書の全ての言葉を“推敲”するんだ!例えば、冒頭の“御社に貢献します”というフレーズを“御社の未来を支えます”に変えるべきではないか?」
山本課長:「いや、どっちでもそんなに変わらないと思いますけど。」
田中部長:「変わる!印象が変わるんだ!だから、全ての表現を検討し直す!」
【推敲地獄の始まり】
(翌日、提案書の修正作業がスタート)
佐藤さん:「部長、目次を“提案概要”にするか“ご提案内容”にするか悩んでます!」
田中部長:「うむ、ここは“提案概要”の方がシンプルでいいな。」
(さらに2時間後…)
山本課長:「部長、本文の『我々はお客様第一です』を『我々はお客様最優先です』に変更しました。」
田中部長:「よし!でも“最優先”よりも“最重要”の方がいいのではないか?」
山本課長:「…また直すんですか?」
(さらに3時間後…)
佐藤さん:「部長!見出しのフォントサイズを16ポイントにするか18ポイントにするかで迷ってます!」
田中部長:「18ポイントだ!いや待て…やっぱり16ポイントの方が品があるか?」
山本課長:「部長、もうこれ以上直したら提出に間に合いませんよ!」
田中部長:「そんなことはない!“推敲”とは徹底的に完璧を追求することだ!」
【ついに提出期限が…】
(提案書の締切が迫る中、田中部長はなおも微修正を繰り返していた)
山本課長:「部長、もう時間です!提出しないと間に合いません!」
田中部長:「待て!最後に“敬具”のフォントを変えるかどうかを決めるんだ!」
佐藤さん:「ええっ!?そこまで細かいんですか!?」
山本課長:「部長!提案書が“完璧”じゃなくても、出さないよりマシです!」
田中部長:「むむむ…仕方ない。今回はこの程度で妥協するか…」
こうして、田中部長が理想とした「完璧な提案書」は完成することなく提出されることになった。しかし、提案書に込めた執念(?)がクライアントに伝わったのか、結果的に商談は成功したという――。果たして“推敲”は営業部に必要だったのか?
まとめ
「推敲」は、ただ表現を練り直すだけでなく、物事を深く考え抜くことの大切さを教えてくれる故事です。文章や作品に限らず、ビジネスや日常生活でもその精神を取り入れることで、自己成長や成果の向上につながるでしょう。